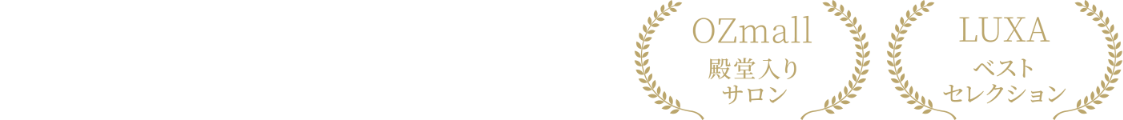アーユルヴェーダとは?健康と美しさをいつまでも保つためのポイント
アーユルヴェーダ

女性なら「いつまでも健康で美しくいたい」と思うものですよね。
しかし、仕事や家事、育児、介護が忙しく、なかなか自分に使う時間がないという人も多いでしょう。
そんな忙しい女性に取り入れてもらいたいのが、アーユルヴェーダです。
この記事では、アーユルヴェーダとはどのようなものか?基本的知識や取り入れ方を紹介します。
いい年の取り方をしたい、いつまでも若々しくいたいという人は、ぜひ参考にしてください。
アーユルヴェーダとは

アーユルヴェーダとは、約5,000年前にインド・スリランカで誕生した伝統的な医学体系のことです。
サンスクリット語のアーユス(Ayus:生命)とヴェーダ(Veda:科学)という2つの言葉からなり、生命科学と訳されることもあります。
アーユルヴェーダは、病気を治すことよりも、今ある健康を維持し、病気になりにくい身体を作る予防医学の考えに基づいて作られています。
食事、生活習慣、運動、瞑想、マッサージなどの日常生活全般から、個々にあったアプローチを行うことで、健康と美しさ、心身のバランスを整え、維持できるのです。
アーユルヴェーダの歴史
アーユルヴェーダは、約5000年前にインドで発祥したとされる伝統医学です。
リグヴェーダとアタルヴァヴェーダと呼ばれる、古代インドの聖典が起源とされ、自然科学や病理学、治療法について記されています。
現在、アーユルヴェーダは体系化された医学としての地位を確立し、他国からも多くの学生が学びに来る国際的な学問となりました。
アーユルヴェーダの効果
アーユルヴェーダは、デトックス効果が高いことから、体質改善に効果的なことは有名です。
老廃物の排出を促し、血流の循環を改善することから、免疫力の強化や消化機能の改善、美容効果も期待できます。
また、アーユルヴェーダは、身体だけでなく心にもよい影響を与えます。
心身のバランスを整えることにより、ストレスの軽減や集中力の向上も期待できるでしょう。
アーユルヴェーダでは予防医学といわれているように、西洋医学では対処しにくい慢性的な問題や未病に対しても効果を発揮します。
アーユルヴェーダで健康や美しさは保てるのか?

アーユルヴェーダで本当に健康や美しさを保てるのだろうか?と疑問に思っている人もいるでしょう。
アーユルヴェーダは、自然と調和し、体内のエネルギーを適切に管理することが重要と考えられています。
体内のエネルギーを適切に管理するためには、体質に合わせた食事や適切な運動、生活習慣の改善などが含まれます。
とくに、体内のドーシャのバランスを整えることが重要で、ドーシャを整えることで体の不調を予防し、美しい肌や健康を維持することができるのです。
また、アーユルヴェーダはストレスの軽減にも効果があるとされています。
過剰なストレスを防ぐことで、健康増進や美しさにも効果を発揮するでしょう。
アーユルヴェーダの考え方

アーユルヴェーダでは、宇宙は空(アーカシャ)・風(ヴァーユ)・火(アグニ)・水(アパス)・地(プルッティヴィ)の「5つ」から構成されていると考えられています。
上記5つの元素の特徴は、以下の通りです。
| 5大元素 | 特徴 |
|---|---|
| 空(アーカシャ) | 軽い・柔らかい・クリア・無限・活動的 |
| 風(ヴァーユ) | 軽い・粗い・クリア・ドライ・冷たい・粗い |
| 火(アグニ) | 軽い・粗い・シャープ・ドライ・熱い・繊細 |
| 水(アパス) | 重い・柔らかい・オイリー・鈍い |
| 地(プルッティヴィ) | 重い・固い・鈍い・鈍い |
そして、身体は小宇宙のため、5大元素から成り立っていると考えられています。
個々に5大元素のバランスが異なり、最適な状態に保つことで、健康を維持できるのです。
アーユルヴェーダ3つの体質

アーユルヴェーダでは、人はヴァータ・ピッタ・カパの3つの体質(ドーシャ)に分かれています。
ドーシャは、5大元素の組み合わせで構成されていて、ドーシャの特性に影響を与えています。
ドーシャの特性は、以下の通りです。
| ドーシャ | 特性 |
|---|---|
| ヴァータ(風・空) | 華奢・冷えに弱い・不眠傾向・乾燥肌・行動力がある・気分屋 |
| ピッタ(火・水) | 中肉中背・暑がり・熱がこもりやすい・情熱的・怒りやすい |
| カパ(地・水) | ふくよか・むくみやすい・鈍感・忍耐強い・穏やか・怠けやすい |
人は、一つもしくは複数のドーシャが優位になっているとされ、ドーシャのバランスを保つことで、健康的な生活が送れると考えられています。
「自分の体質を知る アーユルヴェーダ 体質診断」
⇒ こちらをご覧ください。
簡単にできるドーシャ診断

自分のドーシャがわかると、自宅でもアーユルヴェーダを実践しやすくなります。
下記の表は、ドーシャ診断ができる簡易表です。
最も当てはまる項目が多いものが、あなたのドーシャになります。
自分のドーシャに合った、食事や生活習慣を取り入れてみましょう。
| ヴァータ | ピッタ | カパ | |
|---|---|---|---|
| 体型 | 細身で骨ばっている | 中肉中背で筋肉質 | がっしりとして肉付きがいい |
| 便通 | 不規則で便秘しがち | 下痢をしやすい | 快便 |
| 性格 | 活動的で創造性に富んでいる | 情熱的で競争心が強い | 落ち着いていて堅実 |
| 睡眠パターン | 何度も目が覚める | 短い睡眠で満足できる | いつまでも寝ていられる |
| 気温に対する感じ方 | 寒さに弱い | 暑さに弱い | 湿度に敏感 |
アーユルヴェーダの取り入れ方

アーユルヴェーダは、日常生活にさまざまな方法で取り入れられます。
代表的な取り入れ方は、以下の通りです。
| 食事 | 自分のドーシャに合わせた食事を取ることで、ドーシャのバランスを整えられます。 |
|---|---|
| 運動 | 運動はアグニ(消化)を高め、デトックスの促進や身体の柔軟性、筋力の維持に効果があります。 有酸素運動は、どのドーシャの人にもおすすめです。 |
| 瞑想 | 心の平静を保ち、ストレスを緩和するのに役立ちます。毎日のルーチンにこれらを取り入れることで、精神的な健康もサポートされます。 |
| マッサージ | 肌を保湿し、血行促進、ストレスを軽減する効果があります。使用するオイルは、自分のドーシャに合わせて選ぶのがおすすめです。 |
アーユルヴェーダ的な食事法
アーユルヴェーダでは、「甘味・酸味・塩味・辛味・苦味・渋味」の6つの味が、すべての食事にバランスよく含まれていることが理想とされています。
また、食事を取るときには、心を落ち着け、感謝の気持ちを持つことも大切です。
急いで食べたり、不規則な食生活はドーシャのバランスを崩す原因となります。
また、食後は軽い散歩をするなどして、食べたものが効率よく消化されるよう心がけるといいでしょう。
アーユルヴェーダの食事法は、身体を養うだけでなく、心の健康にもよい影響を与え、日々の生活の質を高める手助けをしてくれます。
ハーブの活用法
アーユルヴェーダでは、体内のドーシャのバランスを整えるためにハーブが使用されます。
ハーブは、消化を助け、ストレスを軽減する効果があり、ドーシャに対応したものを選ぶことで、心身を整えられます。
たとえば、ヴァータの人は、乾燥や冷えやすい体質のため、天草やカルダモンのように、身体を潤し、温める効果のあるハーブが推奨されます。
ピッタの人は、身体に熱をためやすいため、身体をクールダウンしてくれるミントやコリアンダーが最適です。
カパの重さや滞りを解消するためには、カーダモンやフェンネルなどが利用されます。
このように、体質に合わせたハーブを選ぶことで、ドーシャのバランスを整え、心身をよい状態に保てるでしょう。
オイルマッサージのやり方
アーユルヴェーダでは、よくセサミオイルを使用したトリートメントが行われます。
「自分でアーユルヴェーダマッサージができたらな」と考える人も多いでしょう。
そこで、簡単なオイルマッサージの方法を紹介します。
- 1. オイルを手に取り、体温で軽く温める
- 2. 親指で足の裏を滑らせるようにマッサージする
- 3. 足首をつかみ、上下にさする
- 4. ふくらはぎから太ももにむけて、手を滑らせるようにマッサージする
- 5. 手の指を反対の手でつかむようにマッサージする
- 6. 手のひらを親指で円を描くようにマッサージする
- 7. 前腕から二の腕に向かって、手のひらで握るようにマッサージする
マッサージをするときは、末端から中心に向かって行うことで、リンパの流れを改善し、老廃物の排出を促せます。
自分でマッサージをしてみたいという人は、ぜひ挑戦してみてくださいね。
ドーシャ別アーユルヴェーダの実践方法

食事をとるときは、ドーシャに合わせた食材や調理法を選ぶことで、体調を整えることができます。
また、生活習慣についても、ドーシャによって気を付けたいポイントが異なります。
ここからは、ドーシャ別のアーユルヴェーダ実践方法を紹介するので、手軽にアーユルヴェーダを取り入れたい人は参考にしてみてください。
ヴァータの人が取り入れたい食事や生活習慣
ヴァータの人は、冷えやすく、乾燥しがちです。
ヴァ―タを鎮め、ドーシャのバランスを整えるためには、温かく油分を多く含んだ食事を心がけるのがおすすめです。
活動がはじまる朝一番は、身体を温めるスープを取ることで、健康的な1日を過ごせるでしょう。
また、食事の時間や就寝時間を規則正しく保ち、リラックスタイムを確保することも大切です。
過度の刺激や冷たい環境は避け、暖かな場所でリラックスして過ごしましょう。
ピッタの人が取り入れたい食事や生活習慣
ピッタ体質は熱を持ちやすく、刺激的な食品や暑い気候に敏感です。
そのため、適度に身体を冷やす食べ物や、苦味、渋味を含む食材を積極的に食べるのがおすすめです。
ストレス管理も非常に重要です。
冷静さを保つために、日常的に瞑想や軽いヨガを取り入れてみてください。
また、ランニングなどの負荷が重すぎない運動を定期的に行い、体内の熱をコントロールしましょう。
カパの人が取り入れたい食事や生活習慣
カパの人は、体格がよく、潤いの多い体質のため、軽くて乾燥した食品を選ぶのがおすすめです。
辛味や苦味が強い食品を適量取り入れることで、体内の水分と油分を最適なバランスに保てます。
カパの人は、運動でバランスを整えることが大切です。
身体を動かすことでむくみなどの滞りを解消し、心身のバランスを整えられます。
定期的な運動を行い、食べ過ぎに注意し、消化を促す食品を選びましょう。
アーユルヴェーダオイルの効果

アーユルヴェーダで使用するオイルには、デトックス効果やリラックス効果だけでなく、ドーシャのバランスを整える役割があります。
アーユルヴェーダで最もポピュラーなセサミオイルの主な効果は、以下の通りです。
- 保湿効果
- アーユルヴェーダオイルは、乾燥した肌を保湿し、柔らかく滑らかに保ちます。
特にヴァータ体質の人には、日常的なオイルマッサージが推奨されます。
- デトックス効果
- オイルマッサージは、体内の毒素を排出し、血行を促進することで、デトックス効果があります。
アーユルヴェーダでは、特にパンチャカルマという浄化療法でオイルが用いられます。
- リラクゼーション効果
- オイルマッサージは、緊張を緩和し、リラクゼーション効果をもたらします。
ストレス解消や不眠の改善に役立ちます。
- 痛みの軽減
- 関節痛や筋肉痛を和らげるために、アーユルヴェーダオイルが使用されます。
例えば、セサミオイルは温かい性質を持ち、痛みを軽減する効果があります。
- 美容効果
- オイルは、髪の健康を保ち、髪質を改善するためにも使用されます。
アムラオイルやブリンガラージオイルは、髪の成長を促進し、抜け毛を防ぐ効果があります。
アーユルヴェーダオイルの効果を最大限に引き出すために、適切な使用法やマッサージテクニックを学ぶことが大切です。
また、アーユルヴェーダオイルは、使用者の体質や目的によって、ハーブエキスが配合されます。
自分の体質に合ったオイルを選び、日々の生活に取り入れることで、健康と美しさを維持するサポートになるでしょう。
アーユルヴェーダは日本人に合わない?

アーユルヴェーダはインド発祥の伝統的な医学です。
そのため、「日本人の生活や体質には合わないのではないか」と疑問に思う人もいるでしょう。
アーユルヴェーダは、一人ひとりの体質や健康状態に合わせた食事や生活改善を行うため、日本人でも安心して実施できます。
世界的に健康的な生活に関心が高まっているため、アーユルヴェーダはバランスのとれたアプローチができると高く評価されています。
しかし、日本の気候や食文化、生活リズムはインドとは異なるため、アーユルヴェーダをそのまま取り入れるのは難しいかもしれません。
たとえば、インドのアーユルヴェーダで用いられるハーブや食材の中には、日本で入手できないものも多いです。
また、日本の気候の変化に合わせて、実施内容を調整する必要があります。
アーユルヴェーダを簡単に取り入れたいならExpance..のマッサージがおすすめ
アーユルヴェーダは5,000年以上続く伝統的な医学であり、中医学やユニ医学に並ぶ世界三大伝統医学と呼ばれています。
現代においてもアーユルヴェーダの有効性が認められていて、本場インドでは国家資格として認められ、実際に医療の現場で活用されています。
日常生活にアーユルヴェーダを取り入れることで、身体と心のバランスを整え、いつまでも健康と美しさを保つことができるでしょう。
「Expance..について詳しく知りたい方」
⇒ こちらをご覧ください。
「自分の体質を知る アーユルヴェーダ 体質診断」
⇒ こちらをご覧ください。
「ご予約・お問い合わせ」
⇒ お問い合わせください。