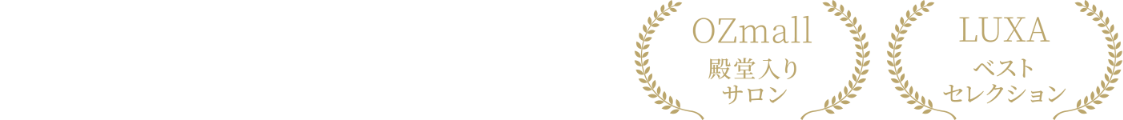アーユルヴェーダマッサージに使うオイルの効果は?おすすめの選び方
アーユルヴェーダ

むくみや疲れの解消など、日々のセルフケアにはオイルマッサージが最適です。
とくに、アーユルヴェーダ式のオイルマッサージは、体質や体調を考慮しながらオイル選びを行うため、身体や心の不調を解消できます。
しかし、ベースとなるオイルやブレンドするハーブは非常に種類が多く、どれがいいのか悩むこともあるでしょう。
そこで、この記事ではアーユルヴェーダによく使用される「ベースオイルとハーブ」の解説や、「体質ごとにオイルを選ぶポイント」を解説しています。
「自宅でアーユルヴェーダマッサージをしてみたい」という人は、ぜひ参考にしてみてください。
アーユルヴェーダオイルとは

アーユルヴェーダオイルとは、アーユルヴェーダ式のマッサージを行う際に使用するオイルのことです。
アーユルヴェーダマッサージには以下のようなメリット」があり、オイルを使ってマッサージをすることで相生効果が期待できます。
- ・デトックス効果
- ・リラックス効果
- ・美肌効果(ハリ・弾力・ツヤ)
- ・疲労回復
- ・体力増強
- ・眼精疲労の改善
- ・快眠
アーユルヴェーダに使われるベースオイルの種類

アーユルヴェーダマッサージに使用されるベースとなるオイルは、主に以下の「5種類」です。
- ・セサミオイル(ごま油)
- ・ギー
- ・キャスターオイル(ひまし油)
- ・マスタードオイル
- ・ココナッツオイル
それぞれの効能やメリットを解説していくので、自分の望む効果が得られるオイルを探してみましょう。
セサミオイル(ゴマ油)
日本のアーユルヴェーダマッサージで主に使用されているのは、セサミオイルです。
肌への浸透に優れていて、成分が老廃物の排出を促します。
セサミオイルの効能やメリットは、以下の通りです。
- ・保湿効果
- ・冷えの改善
- ・免疫力向上
- ・デトックス効果
- ・抗酸化作用
- ・リラックス効果
- ・疲労回復効
- ・美肌効果
- ・抗炎症作用
- ・新陳代謝の向上
ギー
ギーとは、無塩バターから不純物を取り除いたオイルのことで、長期保存が可能な万能オイルのことです。
無数の効果があり、マッサージはもちろん、目薬や食用として用いられることもあります。
ギーの効能やメリットは、以下の通りです。
- ・脂肪燃焼
- ・食欲増進
- ・解毒
- ・ドライアイの改善
- ・便秘改善
- ・抗酸化作用
- ・強壮作用
- ・リラックス効果
- ・疲労回復
- ・解熱
キャスターオイル(ひまし油)
キャスターオイルは健康面で多くの効果を発揮するオイルとして、古くからアーユルヴェーダに使われてきました。
とくに、「座骨神経痛」や「リウマチ」などによく使用されます。
キャスターオイルの効能やメリットは、以下の通りです。
- ・鎮痛作用
- ・抗炎症作用
- ・抗菌作用
- ・抗ウイルス作用
- ・緩下作用
- ・抗酸化作用
- ・デトックス作用
- ・神経痛
- ・便秘改善
- ・瘢痕形成作用
マスタードオイル
マスタードオイルは、「ドーシャを鎮静させる効果」があるとして、古くからインドで食用として親しまれていました。
欧米でも、マッサージオイルとしてよく使用されています。
マスタードオイルの効能やメリットは、以下の通りです。
- ・抗炎症作用
- ・小じわの改善
- ・美白効果
- ・育毛促進
- ・抜け毛予防
- ・白髪予防
ココナッツオイル
ミネラルが豊富なココナッツオイルは、古くからコシのある艶やかな髪になれるとして、アーユルヴェーダでは頭皮マッサージによく使われていました。
「身体を冷やす効果」があるので、夏場のマッサージオイルに最適です。
ココナッツオイルの効能やメリットは、以下の通りです。
- ・ストレス改善
- ・血行促進
- ・美髪効果
- ・美肌効果
- ・抗炎症作用
- ・新陳代謝の向上
- ・脂肪燃焼
- ・抗酸化作用
- ・紫外線予防
- ・抗菌作用
不調の改善には薬草オイルがおすすめ

アーユルヴェーダマッサージは、体質や体調を考慮してマッサージを行うために、薬草エキスを溶け込んだベースオイルを使用します。
薬草の成分が肌から浸透して、身体や肌の不調を改善できます。
ここでは、不調の改善におすすめのハーブを紹介するので、よりマッサージの効果を感じたいという人はためしてみてください。
マハナラヤナ
マハナラヤナは、筋肉痛や肩こりに効果抜群のハーブです。
筋緊張からくる身体の不調に悩んでいる人におすすめ。
また、免疫機能向上や内臓機能向上効果も期待できるため、内臓の疲れや免疫低下になやんでいる人にもおすすめできます。
ニーラ
抜け毛や髪のコシ・艶など、頭髪の悩み全般に効果のあるハーブです。
炎症を鎮静する効果もあるため、肌の炎症や頭髪に悩みを抱えている人におすすめです。
また、めまいにも効果を期待できます。
ピンダ
ピンダには、疼痛を緩和する効果が期待できるため、身体の痛みに悩んでいる人におすすめです。
抗菌・抗炎症作用や創傷治癒効果もあるため、「切り傷」「肌荒れ」をしているときでも使用できます。
アシュヴァガンダ
アシュヴァガンダには、ストレス緩和や免疫力向上効果があり、不定愁訴に悩んでいる人に最適なハーブといわれています。
身体の適応力やストレス耐性を高めることから、ストレスによる不調が身体にまででているという人におすすめです。
トリパラ
トリパラは、心や身体のバランスを整え、痛みや不調を改善する効果が期待できます。
便秘や下痢、食欲不振、肌荒れに悩んでいる人におすすめです。
サルサパ
サルサパは、リウマチや関節痛、外傷性のむくみに効果を発揮するハーブです。
節々の痛みに悩んでいる人におすすめで、筋肉のコリやハリによる痛みを緩和する効果も期待できます。
体質ごとのオイル選びのポイント

これまで、アーユルヴェーダで使用されるオイルや薬草を紹介してきましたが、「種類が多いため、どれを選んだらいいのかわからない」と悩んでいる人もいるでしょう。
体質や体調ごとにオイルを使い分けると、よりマッサージの効果を実感できます。
ヴァータ・ピッタ・カパタイプごとにおすすめのオイルを紹介するので、参考にしてみてください。
ヴァータタイプ
ヴァータタイプは体調が移り変わりやすく、「冷えやすい体質」です。
そのため、身体を温めてくれるオイルやリラックス効果のあるオイルやハーブを選ぶといいでしょう。
- ・セサミ
- ・アーモンド
- ・ヒマシ
- ・マハナラヤナ
- ・アシュワガンダー
ピッタタイプ
ピッタタイプは「身体に熱が籠もりやすい」ため、身体を冷やす効果のあるオイルを選ぶのがおすすめです。
また、頭に血が上りやすいため、ストレスを緩和する効果のあるハーブを選ぶようにしましょう。
- ・ココナッツ
- ・オリーブ
- ・ヒマワリ
- ・ブラーフミー
カパタイプ
カパタイプは「身体に水分をためこみやすい」ため、デトックス効果のあるオイルを選びましょう。
また、「体重が増えやすい」ため、脂肪燃焼や新陳代謝向上効果があるハーブを選ぶのもおすすめです。
- ・ショウブ
- ・マスタード
- ・アマニ
アーユルヴェーダオイルの効能をアップさせる使い方

アーユルヴェーダオイルは、正しい使い方をすることでその効果を最大限に引き出すことができます。
マッサージやヘアケア、フェイスケアに取り入れることで、体の内側から健康と美容をサポートしてくれることが魅力です。
オイルの種類や使用方法を工夫することで、心身のバランスを整え、リラックス効果やデトックス効果を高めることができます。
ここからは、アーユルヴェーダオイルの効果的な使用方法を紹介します。
オイルマッサージを行う
オイルマッサージ(アビヤンガ)は、アーユルヴェーダの伝統的なセルフケアです。
温めたオイルを全身に塗布し、優しくマッサージすることで、血行促進やデトックス効果を高めます。
オイルマッサージは、体内の毒素(アーマ)の排出を促し、エネルギーの流れをスムーズにしてくれます。
朝に行うことで、すっきりと、リフレッシュした1日を過ごせるでしょう。
マッサージに使うオイルは、ドーシャに合わせて選ぶことが大切です。
ヴァータ体質の人はセサミオイル、ピッタ体質の人はココナッツオイル、カパ体質の人はマスタードオイルを選ぶのがおすすめです。
定期的にオイルマッサージを行うことで、身体の緊張をほぐし、肌に潤いが生まれます。
リラックス効果も高いことから、身体と心、両方のよい影響が期待できます。
ヘッドマッサージに使用する
アーユルヴェーダというと、オイルを使ったヘッドマッサージを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
頭皮にオイルをなじませ、優しくマッサージすることで、ストレス軽減や頭皮の血行促進、美髪、美肌効果が期待できます。
とくに、夜ヘッドマッサージを行うことで、良質な睡眠を取る手助けとなります。
使用するオイルは、セサミオイルがおすすめです。
セサミオイルは、頭皮の血行を促進し、抜け毛の予防や髪の成長をサポートします。
また、温めたオイルを使うことで、毛穴が開き、有効成分がより浸透しやすくなります。
ヘアケア・フェイスケアに使用する
アーユルヴェーダオイルは、ヘアケアやフェイスケアにも優れた効果を発揮します。
髪に塗布すると、乾燥やフケを防ぎ、ツヤのある健康的な髪を維持できます。
また、フェイスケアに使用すると、肌の保湿やエイジングケアに効果的です。
アーユルヴェーダの王道セサミオイルは、抗菌・抗炎症作用があり、ニキビや肌荒れを防ぐのに適しています。
オイルを顔に塗布する際は、やさしくマッサージしながらなじませると、血行が促進され、より効果を発揮しやすくなります。
アーユルヴェーダオイルの作り方

アーユルヴェーダオイルは、自宅で作ることもできます。
実際に、アーユルヴェーダの本場インドでは、バターを煮つめてギーを作ったり、ベースオイルにハーブエキスを配合したりして、アーユルヴェーダオイルを常備薬のように使用しています。
ここでは、アーユルヴェーダの王道「セサミオイル」の作り方を紹介するので、ぜひベースオイル作りに挑戦してみてください。
- 材料
- ・白ごま油
- ・鍋
- ・遮光瓶
- 作り方
- 1. 白ごま油を鍋に入れ、弱火にかける
- 2. 温度計がある場合は、ごま油が90度になるまで煮つめる
- 3. 温度計がない場合は、1分を目安に火からおろす
- 4. 遮光瓶にいれ、冷暗所で保管する
アーユルヴェーダオイルについてくわしく知りたい人は、下記の記事も参考にしてみてください。
アーユルヴェーダオイルを使用するときの注意点

アーユルヴェーダオイルは、正しく使用することで効果を最大限に発揮します。
しかし、間違った使い方をすると逆効果になることもあるので注意が必要です。
アーユルヴェーダオイルの注意点をお伝えするので、自宅で使用する人は確認しておきましょう。
ドーシャに合わないオイルは不調が悪化してしまう可能性がある
アーユルヴェーダでは、「ヴァータ・ピッタ・カパ」の3つのドーシャに基づいてオイルを選びます。
ドーシャに適したオイルを使用することで、心身のバランスを整えることができます。
しかし、間違ったオイル選びは体調を崩してしまう原因になる可能性があるので、注意しなくてはいけません。
たとえば、ヴァータ体質の人が乾燥しやすいココナッツオイルを使うと、さらに乾燥を悪化させることがあります。
そのため、自分のドーシャを正確に診断し、ドーシャに合ったオイルを選びましょう。
アレルギー体質の人は症状の出ないオイルを選ぶ
アーユルヴェーダオイルには、多くの天然成分が含まれています。
人によっては、アレルギーを引き起こす可能性があるので、体質に合わせてオイルを選ばなくてはいけません。
使用前には、パッチテストを行うなどして、肌に合うかを確認しましょう。
オイルは酸化しやすいため適切に保存する
アーユルヴェーダオイルは、時間がたつと酸化してしまいます。
そのため、直射日光を避け、冷暗所で保存することが大切です。
とくに密閉状態にないものは、できるだけ早めに使い切るようにしましょう。
市販のオイルは信頼できるお店で購入する
市販のアーユルヴェーダオイルの中には、品質の低いものや、保管状況の悪いものが販売されていることもあります。
品質の悪いアーユルヴェーダオイルを使用すると、肌荒れや体調不良を引き起こす原因になります。
信頼できるメーカーやお店の製品を選び、安全に使用することが重要です。
本格的なアーユルヴェーダオイルマッサージなら「Expanse..」へ
この記事では、アーユルヴェーダマッサージに使用する「ベースオイル」や「ハーブの効果・メリット」を紹介しました。
自分にぴったりのオイルやハーブでマッサージを行うことで、よりマッサージの効果を実感できます。
しかし、自分に合っているオイルを探すのは骨の折れる作業ですよね。
Expanse..では、カウンセリングにて一人ひとりに合ったオイルを調合してマッサージに使用しています。
「本格的なアーユルヴェーダオイルマッサージを受けたい」、「自分に合ったオイルでケアしたい」という人は、Expanse..にご相談ください。
「Expanse..について詳しくはこちら」
⇒ お問い合わせください。
「ご予約・お問い合わせ」
⇒ お問い合わせください。